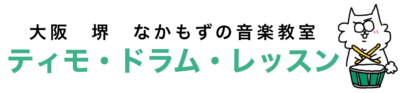高校生の頃に聞いていた、ミスチルやスピッツといった邦楽バンドの、最近のライブ映像を見た時のことです。ミスチルは『Not Found』、スピッツは『冷たい頬』を演奏していました。どちらの曲も、リリースされたのは15年ほど前です。多少アレンジしているとはいえ、両バンド共に、15年もの間ずっと同じ曲を演奏していることになります。
僕が初めてバンドで作曲したのは、ドラムを始めて半年ちょっとの頃で、10年くらい前のことです。作った当時は、「良い曲ができた!」とウハウハだったのですが、今となっては恥ずかしくて聞けないくらい、稚拙な曲でした。ちなみに、ジャンルはパンクです。オープン・コードを、ストラトのクリーントーンでじゃかじゃかやってあたりが一番パンクだったと思います。
そんな自分の体験と比べるのは、はなはだおこがましいことですが、自分が10年以上前に作った曲を、当時のエネルギーを維持したまま演奏し続けるなんて、正気の沙汰ではありません。途中で飽きるやろ、と。ストーンズなんて、もう半世紀近く『Jumpin’ Jack Flash』をやっています。そらドラッグに手を出したくもなるわ、と。

正気の沙汰ではない、とは言いましたが、これは非難ではなく、むしろ敬服です(ドラッグはどうかと思いますけれど……)。最近、演奏していて感じるのは、いくら実力をつけたとしても、最終的に良い演奏ができるかどうかは、心の在り様によって決まるということです。その点、すごい人は常軌を逸して「音楽愛」を持っているんだな、と思います。
ただ、同じ曲をずっと演奏し続けることだけが音楽愛ではありません。新しい音楽を日々創り続けるのも音楽愛です。ライブの音響や照明、販売や広告など、音楽に関するものすべてに、音楽愛は関係しているのです。共通して言えるのは、「音楽を愛し続けている」ということです。愛とはすなわち、忍耐です。