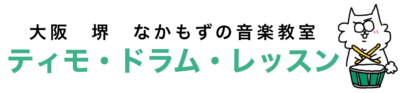もともとは「電車オタク」など、ある特定の分野において、趣味が突出している人物のことを指した言葉でした。現在は、アニメ、漫画、ゲームオタクを指す場合が多いです。英語でも、「Otaku」という単語が意味するのは「日本製アニメや漫画などの熱心なファン」と、分野が限定されています。
何を隠そう、僕もゲームオタクです。スティックを握るずっと前からゲームボーイを操っていましたし、ジャズと出会った書店へ行っていたのも、ゲーム雑誌が目的でした。ゲームをしていなければジャズに興味を覚えることはなかった、と言っても過言ではありません。
今や「日本のオタク文化」と呼称されるほど、オタクは代表的、大衆的、一般的なものになりました。しかし、現在のオタクと20年前のオタクは、必ずしも同じものではありません。たとえば、現在のオタクは、「ロボットアニメ好きのAくんと魔女っ娘アニメ好きのBくんが、自分の分野の良い点を理解しない相手を蔑んだり、逆に相手の分野の悪い点を挙げたりして言い争う」といったことがあります。しかし、昔のオタクは、「自分の分野をよく知りもしないのに知った風な素振りをする」、いわゆるニワカに対して怒ることはあっても、自分の趣味を押し付けたり、ましてや、相手の分野をけなしたりすることはまれでした。

そもそもオタクとは、あくまで趣味に没頭することが目的であって、他人の理解や共有は不要でした。自分の世界を深く掘り下げるために、同じ分野のオタクとコミュニケーションを取ることはあっても、分野の違う相手と言い争うことは無意味なのです。ところが、現在のオタクは、「自分の趣味を幅広く知ってもらいたい」「誰かの趣味に共感したい」という、趣味の共有化が進んでいます。近年、女性のオタクが増えているのも、これに起因しているのではないでしょうか。
このような変化は悪いことではありませんが、長くは続かないように思えます。また10年もしないうちに、今度は趣味の固有化が進むでしょう(現在もその傾向があります)。そして、この固有化は趣味の世界に留まらず、あらゆる事柄に対し適用されます。固有化が最も安定しているからです。安定や安心を求めるのは、今も昔も変わっていません。